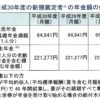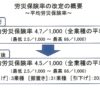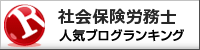過去問に始まり過去問に終わる
勉強の中心教材となるのはなんといっても、基本書と過去問です。進め方としては、さっと基本書に目を通す。あくまでも最初はかるく目を通すくらいでいいです。理解できなくてもあまり深く考えず、「あぁ こんなこともあるのか」と思い読み進めます。
それから過去問を解き始めます。補足事項や重要ポイントがあればドンドン基本書に書き加えていきましょう。過去問を解きながら基本書を詳しく読み込んでいくイメージです。
最初に基本書を読んだ時にまったく理解できなかった部分も、しだいに分かるようになってきます。
コツとしては分からなくても深く考えないこと、立ち止まらないことです。「やっているうちに分かるようになるさ」と思い楽観的に進めていきましょう。
勉強を進めていき知識がふえていくにつれ、様々な情報が結びついてある日ピタッとはまる時がきます。もし試験近くになって、どう考えても分からないところが残ってしまっても、「この部分は試験にはでない」と割り切りましょう。
試験範囲の全部が出題されるわけでもなく、ましてや満点を取る必要もないからです。基準に達し合格すればそれでよいのです。悩んでいる時間がもったいないです。

問題集を何冊も購入する必要はありません。解説のしっかりした過去問題集が一冊あれば十分です。一回全部やってもすべて理解できるものではありませんし、もう一回やってみるとかなり忘れている場合がほとんどです。
また一冊を何回もこなしたほうが記憶に残ります。「あのページのこの部分に似た問題があったな」「この図は解説のところにあったものと同じだ」などイメージとして画像が浮かぶようになればしめたものです。
過去問は試験のエッセンスがギュッと詰まっています。毎年必ず出題される所とそうでない所、引っかけとして使われる場所、その試験独特の言葉づかいなどを理解することができます。
何回も過去問を解いていくうちにだんだんと出題の傾向やクセが見えてきます。そうすることにより勉強の時間配分も変えていくことができますし、見え見えの引っかけもすぐ気づくようになります。
基本書を読んでいるだけでは分からない試験のテクニック的な部分も過去問を解くことによってしだいに身に付いてきます。
過去問を解く回数に比例して点数は伸びていき、そして合格に近づきます。過去問を解くことは基本の勉強法であり、最大の効果をもたらすでしょう。
ポイント
過去問を制する者は、試験を制します!出題個所はもちろんのこと、言葉の言い回し、年度別の傾向など試験の情報がたっぷりつまっています。ですので過去問を解いた回数で合否が決まると言っても過言ではありません。
スポンサーリンク
公開日:
最終更新日:2020/09/03